ジャズからポップスまで、幅広いジャンルを歌いこなす! シンガーは初めてのインタビュー。2026年最初に注目したアーティスト、今田学の歌を聴け!
私が彼の歌を最初に聴いたのは、昨年5月。今田学(Vo)、伊藤駿介(Pf)、越野振人(Ba)、鈴木梨花子(Dr)の4人からなる、Ours4というユニットだった。彼の歌声は、非常にしなやかで、優しく、ジャズのユニットなのだが洋楽のポップスのシンガーのような印象を受けた。それがきっかけで少し交流を持つようになると、佐賀県で生まれ広島大学に通っていた彼は、私のニューヨーク時代の親友でこのサイトでもインタビューを掲載している広島県出身のジャズ・ギタリスト、高免信喜くんと広島で繋がっているということがわかり話が弾んだ。
それが縁となり、今回インタビューを申し込んでみると、「僕、そんなにジャズじゃないですけどいいんですか?」と返ってきた。私は、気にすることはない、私自身そんなにジャズではないし、このサイト自体それほどジャズでもないのだからと答えた(実際、SPECIAL CINTENTSではシティ・ポップスのシンガー和田加奈子さんのインタビューも掲載している)。それでインタビューが決まり、改めて彼の歌声を探してみると、私の大好きなポール・マッカートニーや、キャロル・キングのカバーが印象に残った。やはり最初に感じた“洋楽のポップスっぽい”という私の印象は外れていたわけでもなさそうだと思った。

(撮影・原宿~代々木公園)
そんな彼が音楽を始めたきっかけ、歌を始めたきっかけから話を聞いてみた。
「音楽を始めたのは、佐賀の実家でよくいろんな音楽が流れていて、テレビとかから流れてくる音楽を聴いて、それを歌っていたのがきっかけです。そこから、ギターを買ってもらって、ギターを練習するよぅになりました。その後は、高校生になって吹奏楽部に入って、トロンボーンを吹いていました。そこが人前で演奏した初めてだったですかね? それで、初めて歌で好きになったのはウルフルズで、あとは、当時テレビに出ていて流行っていたポケットビスケッツとかブラックビスケッツとか、その辺からJ-POPはいっぱい聴きましたね。それに、その頃から今でも好きな山下達郎さんとか、サザンオールスターズも聴いていました」
現在は、ピアノの弾き語りが彼のスタイルになっているが、歌をうたったきっかけは何だったのだろう?
「吹奏楽部が、ポップスやミュージカルなんかも演奏してたんですよ、クラシックの他に。そのミュージカルの曲で歌ったのが、人前で歌ったのが初めてだったと思います」
高校時代に吹奏楽部の演奏の中で、歌うことの楽しさを覚えた彼は、大学進学で地元・佐賀県を出て、広島大学に入学する。
「大学に入ってからは、合唱のサークルや、他にも、大学の広場でサークルのバンドが演奏していて、その時に見ていたバンドに入れてもらったりもしていました。あとは、ジャズ研にも入っていましたし。ジャズに関しては、中学や高校の吹奏楽部でもジャズを演奏するところも多いですしね。その吹奏楽部でジャズの入り口にはいたんですけど、ちゃんとジャズを聴くようになったのは、それ以降のことですね」
前に書いた通り、ギターから音楽に入った彼は、今ではピアノの弾き語りを自分のスタイルとしている。
「ピアノを弾くようになったのは、ジャズをやるにあたって、ハーモニーがわからないと難しいかな? と思いました。それで、ハーモニーをちゃんと勉強するのにピアノを弾かなければいけなかったのと、合唱のサークルでは指揮もしていたので、そのリハーサルで自分でピアノを弾いて音を確認しなきゃリハができなかったので、それがきっかけでしたね」
その後、彼は広島市内のライヴハウスなどで歌うようになる。
「大学生の頃は音楽サークルにたくさん入っていたので、それぞれ一つひとつの活動で忙しくて(笑)。その頃は広島県の大学で広島市にたくさんライヴハウスがあって、そっちの方に遊びに行っている時に広島に“ピアノバー下本”っていう、下本滋さんっていうピアニストがやっているお店があって、そこで「歌ってみるかい?」って言ってもらえました。実は、大学を普通よりもちょっと長く行っちゃってて(笑)、その長く行っている時間に、外でちゃんと歌い始めたっていう感じですかね? その頃は、ジャズのスタンダードばかり歌ってました」
その大学時代、広島で歌い始めた頃から、彼は次第にジャズの魅力を知るようになったようだ。
「ジャズ・スタンダードに関しては、今は仲間4人でやっている「Ours 4」というユニットでやらせてもらっている感じです。まあ最初の頃から、ポップス以外にもいろいろやってみたいという気持ちがありました。でも、他人から見れば僕は雑多な感じに見えるでしょうね(笑)」
そして、大学卒業後も、しばらく広島で活動を続けることになる。
「2014年に大学を卒業して、そこから2020年まで広島にいました。大学卒業後は、ヴォーカル教室で教えていたのと、自分が歌ったり演奏したりというのが仕事という感じでしたね。大学卒業後も、会社員とかはやっていないんです。だけど、生活は超ぎりぎりでしたね(笑)。最初に所属させて頂いたヴォーカル・スクールが、ちゃんとレッスンをさせてくれるところだったので、まあそこを頑張れば生活は良くなるかな? というイメージでやってはいたんですけど。その頃は自分で組んでいたユニットがいくつかあって、それはジャズじゃなかったですね。ポピュラーをお洒落にやっていたユニット。で、もうひとつ、ヴォーカルとピアノの女の子と3人でポップスをやるというユニットをやっていました」
その後、東京へ出てくるのだが、その直後、世の中はコロナに襲われることになる。
「東京に出てきた、ちょうどそのタイミングで世の中がコロナになってしまいました。なので、それ以降、ひとりで音楽をやっているという感じですかね。ちょうど東京に引っ越したタイミングだったんですよね。だから東京に来て、1年以上まったく何もできなかったんです。その間、ヴォーカル・レッスンもできなかったですしね…」
そして、コロナ過が明け、以前からつき合いのあった、同じ歳のピアニスト伊藤駿介とともに、ジャズの方向へと進んで行くことになる。
「ジャズはやりたかったので、いくつかお店にアプローチしたことはあります。渋谷のライヴハウスで、今Ours 4で一緒にやっているピアノの伊藤俊介くんと、彼は同級生なんですけど、彼と一緒にやっていく中で4人のユニットのOurs 4になっていったんです。伊藤くんは、僕から一緒にやりたいって誘いました。最初に4人で音を出したのは、去年の頭だったかな? まだ数回しかライヴもやっていないですが、みんな、僕以外は毎日どこかのお店で演奏しているようなプレイヤーたちなので、僕がもっとちゃんとジャズをやらないといけないなっていう印象はありますが。他のメンバーが、僕のアレンジを面白がってくれていて。曲数でいうと僕のアレンジが今のところ多いんですよ。今後は、レパートリーを増やしつつ、オリジナルもやってはみたいなと思っているんです。ただ、やるなら英語でやりたい気持ちがあって、ちょっとその辺はハードルになってはいるんですけどね。みんなで話をしているわけではないですが、僕個人としては、このユニットはずっとやり続けて行きたいなと思っています」

Ours4 1月25日池袋INDEPENDENCE
http://jazz-independence.com/
今回、今田くんをインタビューしようと思ったきっかけに、Ours4での演奏、高免くんとのこと以外に、もうひとつ、昨年末に行われた配信の音楽によるコンテスト『音家ぐらんぷり2025 with TuneCore Japan』で、彼が応募した楽曲「just in time feat. 藤原洋輔」が優秀賞を受賞したということもあった。
「今、僕が配信しているのは、そのTuneCore Japanからなんですね。それで、お知らせが来まして、その中に今回のコンテストを見つけて、あっ面白そうだなって思って応募してみたんです。一緒にやった藤原洋輔くんとは、一昨年の4月くらいに知り合いになったんですけど。その彼を共通の知人を通して紹介してもらって、何か1曲一緒にやりませんか? って僕から誘いました。同じ歳なんですよね。彼はギターも弾きますが本当は何でもできて、本職はドラマーで、ギターも弾けて、ベースも弾けて、歌も上手で、配信のジャケットのイラストも彼なんですよ。で、今回は、ミックスもマスターも彼にお願いしていて。だから、全行程を通して、僕らふたりしか関わっていないんです。僕が作詞作曲をして、ある程度のデモ音源を元に、細かいアレンジはふたりで決めてという感じでした」
今回の受賞を、どう感じているのだろう?
「まあ、ビックリはしましたね。最初にリスナーからの投票があった時は、そんなに上の方にいなかったんですよ。今考えると、その時は賞を取れるとは思ってなかったかもしれないですね(笑)。受賞後は、少しみなさんに聴いて頂いてる感触はあります。それで、聴いてもらって、そこからライヴに出ませんか? みたいなお誘いがあれば嬉しいですね」

https://linkco.re/YQstUvxn
彼は、自分自身が歌うこと以外にも、楽曲提供やアレンジャー、プロデューサーとしても、自身の音楽活動の幅を広げている。
「今年は、すでにキーボードのNamito Yoshidaさん、ヴォーカルの和美珠世さん、このおふたりと共作でリリースするものが決まっています。あと、この間録音した自分個人のものも、3月くらいにはリリースする予定です。こちらは、今田学名義で出します。なので、今年も個人としては、今までのようなスパンでリリースとライヴを続けて行けたらいいなという気持ちでいます。僕は活動量を増やすというよりも、一つひとつの活動のクオリティを上げて行って、作品もいいものを作って行けたらいいなという気持ちが強いんですよ。それで、結果的に今よりも音楽活動が忙しくなればいいなとは思いますが、自分としては活動の内容の方が気になりますね。あとは、一昨年くらいから少しずつ他のアーティストさんのアレンジなどに関わったり、コーラス・アレンジをしたりとか、そういう仕事も好きなので、これからもっとやって行けたら嬉しいなという気持ちはありますね」
今回、今田学というシンガー、ミュージシャンを取り上げさせてもらったが、彼はジャズという枠には収まらないアーティストだ。広く音楽をやり続ける中で、ジャズに出会い、彼自身がその魅力を知り、ともに演奏する素晴らしい仲間たちに出会ったことで、ジャズ・シンガーという側面も持つようになっただけなのだ。でも、私はそういう、今田くんのようなミュージシャン、アーティストが好きだし、私の好み、このマガジンの本道だとも思っている。今回、今田学というシンガーを取り上げることができて、本当に良かったと思う。このインタビューが、このサイトの今後の指針になってくれればいいと感じている。
https://manabuimada.wixsite.com/manabuimada
https://www.tunecore.co.jp/artists/manabuimada
今後のライヴ予定:2月20日(金)下北沢Laguna
https://s-laguna.jp/
※その他、今田学くんの今後の予定に関しては、HP及びSNSで。本サイトでも、随時告知して行こうと思います。
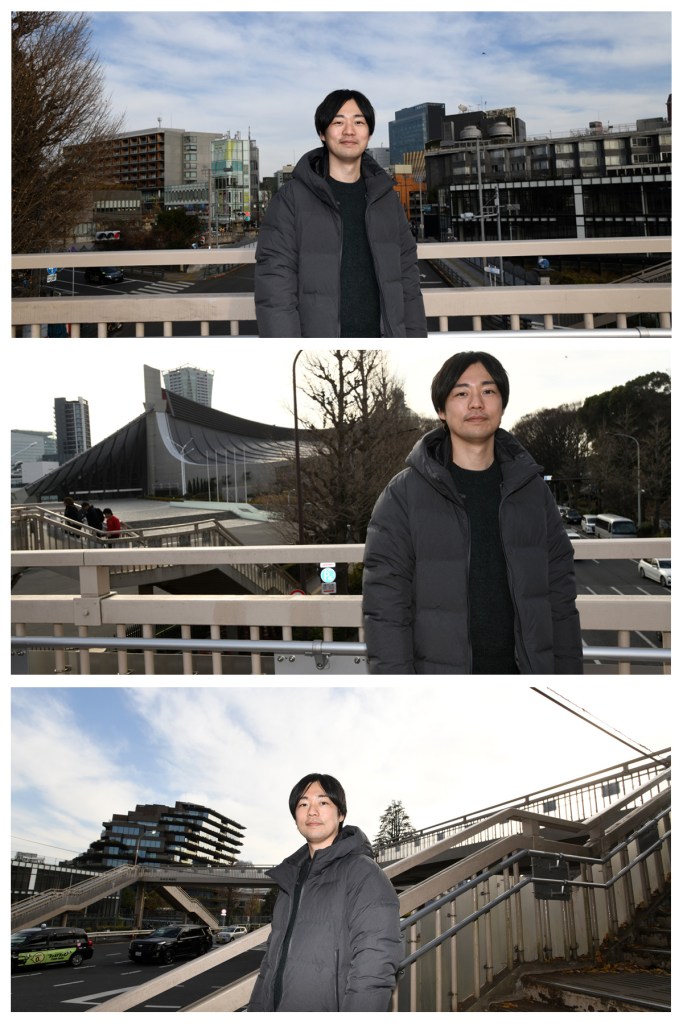
ドラマー山田祐輔は、ナチュラルな人間としての魅力を備えていると感じる。今回はこちらからの希望で話を聞き、彼の持っているその魅力について探ってみた。
ドラマー山田“ローソン”祐輔という男。私は、このweb magazineを立ち上げるために、若いジャズ・ミュージシャンたちのライヴに顔を出すようになり、スタートしてからも、ライヴ会場で若手ミュージシャンたちから、共通の知り合いとして、あるいはこのサイトを見て「知ってます!」といって必ず名前が挙がるのが彼だ。知り合う人、人、人、みんなが「ローソンさん! ローソンさん!」といって、そろって彼の名を口にするのである。
そんなことが続いていたので、私はその同世代からの絶対的な知名度、彼に対して溢れる親近感、信頼感、その理由を知りたくて、今回は私の方から「ぜひに!」ということで、インタビューをお願いした。ここでは、その山田くんのミュージシャンとしての魅力、そして人間としての魅力に迫ってみたい。
まずは、彼の音楽のルーツと、ドラムを叩き始めたきっかけから話を聞いてみよう。
「小さな頃、母親にいろいろ聴かされていたんですよ、80’sの洋楽とか。そこからだと思うんです。僕、ピアノをやっていたんですよ。けど、ピアノが本当に嫌いで(笑)。それですぐにやめてしまって。その後に~小学校3年生とか4年生とかですけど、その頃にアース・ウィンド・アンド・ファイアーとかを母親から聴かせられていて。ジャズではないですけど、アメリカン・ポップスみたいなものが、凄く入ってきたなっていう印象がありますね。それで、嫌いなピアノはやめてしまって、小学校4年生くらいの時に、母親が今度は「お前はタイコでも叩いてみたらどうだ?」と言ったんです。それで、僕は親には従順なタイプだったので(笑)、はい、それではやりますと言って、タイコを叩き始めたっていう。なので、タイコが好きになってっていうよりは、言われるがままに叩いていた感じですね。それで、たまたま自分の中で、タイコが凄くハマったっていう感じなんです」
母親から音楽的に影響を受け、ドラムを始めた彼は、中学でブラスバンド部に入部する。その時に出会ったのが、彼が音楽的に影響を受けたというT-SQUAREだ。
「T-SQUAREの楽曲っていうのは、吹奏楽の定番だったので。そこで、有名な「宝島」っていう曲とかに影響されて、インストロメンタルにハマって行くんです。当時、YouTubeの動画で見た、T-SQUAREの衝撃が今でも忘れられないんです。僕は吹奏楽部で、サックスのある音楽だから、尚更ささってしまって、“ヤバイ!カッコ良すぎる!”ってなって。その時のことが、今でも忘れられないです」
多くのジャズ・ミュージシャンたちから、影響を受けたアーティスト、バンドとしてT-SQUAREの名前が挙がることは多いが、「ジャズではないよね?」ちょっと意地悪に振ってみると、彼はこう答えた。
「T-SQUAREがジャズではないっていうのは、後からわかりました。でも、ジャズではないですけど、インストロメンタルじゃないですか? 凄くカッコイイって思ったんですよね。それで、則竹裕之さんのセッティングの真似をしたりして、それぐらい衝撃的で、好きだったんですよね」
確かにT-SQUAREの音楽、プレイにはジャズを志すミュージシャンたちの心にも、刺さるものがあるのだろう。私は、正直言ってそれほど詳しくないのだが、いろんなミュージシャンたちから同じような話をたくさん聞いていているので、そのことは理解できるつもりだ。彼は、こんなふうに話を続ける。
「亡くなった母親が、高中正義を聴いていたっていうのを父親から聞きまして。それで多分、母親はT-SQUAREも知ってただろうなって、後から思ったんですよね。その頃、僕はまだT-SQUAREを知らなかったですから。僕は中学生で母親を亡くしているので。小さな頃の自分にとっては、母親の影響って凄く大きかったんです」
宮城県仙台市出身の彼は、中学で吹奏楽部に入部して、T-SQUAREと運命の出会いを果たし、高校卒業後に東京の音楽大学へと進むこととなる。
「T-SQUAREの他にカシオペアも好きだったんですけど、当時テレビにカシオペアのドラマーの神保彰さんが出ていて、その神保さんが大学で教えているというのを知ったんです。で、その憧れの神保さんに習いたくてですね。なんですけど、その頃、同時にカシオペアとT-SUAREを聴いていて、T-SQUAREの則竹裕之っていうドラマーのことをちゃんと調べて、音楽性が則竹裕之の方がいいなと思ったんですね。だから神保さんが悪いってわけじゃなくて、こっちの方が好きだなと。で、ある時調べたら則竹さんも大学で教えているなと。それで、プロ志望というのではなく、この人にドラムを習いたいという、それだけで音大に行ったんです。それが、実は大学に入ってからの悩みにもなったんですけど。ドラムを習いたかっただけなのに、いざ習える環境になって、大学に入ってまわりを見たらみんながみんなプロ志望で、「これは間違ったかな?」と思いましたね(笑)。則竹さんに会えたのはいいんですけど、このままじゃここで自分は終わっちゃうんじゃなかと・・・そんな感じだったので、大学の1~2年は、授業についていくので精一杯だったんです」
それでも、彼は強い音楽への憧れ、気持を持って、徐々にそんな環境にも対応していく。
「大学は6年行ってるんです。4年間ジャズ科に行って、あと2年クラシックをやっているんです。正直言うと、当時はジャズ科を4年やって、そこで社会に出て行く自信がなかったんですよね。で、吹奏楽をやっていたのでオーケストラにも興味があったので、2年間伸ばしてやれるだけやろうと思ったんです。そこで、さらにクラシックの打楽器を習ったってことで、ドラムを含めた打楽器奏者としての自信がつきました」

彼の世代は、二十代半ばという大事な時期をコロナに襲われ、彼も音楽活動ができなくなり、そうとうまいっていたようだが、そんな中でも、出場した浅草ジャズコンテストでは2年連続で実績を残した。
「賞を取ったのは、2021年と2022年ですね。当時、慶應義塾大学のビッグバンド・サークルに参加していて、その時の仲間と出ようということになったんです。それで僕とベースと、鈴木雄太郎さんという今ジャズの世界でむちゃくちゃ有名になったトランペットがいるんですけど、その3人で出ました。コードレス・トリオで、ピアノのデューク・エリントンをやるっていう、凄く攻めたことをやった。ピアニストの曲をコードレスで(笑)。それで、第2位でした。その翌年も、慶応のビッグバンドで出場して3位でした。毎回、テッペンでもなく、ちょっと微妙な位置っていう(笑)、そんな感じでしたね。やっぱり1位を取りたかったです」
やがてコロナ過が明け、演奏に明け暮れることができる生活となった今、彼は何を、どう考え、感じているのだろうか?
「充実しているか、していないかって聞かれたら、していると思います。今、CDを作りたいと思っています。メジャー・デビューしたいなって感じではないんですけど。自分の名刺がない状態なんですよね、曲は作ってるんですけど」
彼はリーダー・ライヴのたびに、新曲を披露するということを自分に課しているという。
「自分のトリオをやり始めて、不定期ですけど、それで曲も頑張って作っていて。僕は、ジャズは書けないです。ポップスしか書けないのです。ジャズは好きですけど、でも、ジャズを押しつけることはしたくないんです。それはそれで、まだまだお客さんに受け付けてもらえないこともありますし、難しいですね」

彼と改めて、じっくり話をしてみて感じたのは、凄く控え目なところはあるけれど、意外と、思っていたよりも普通なんだなということ。人から好かれる、同世代の心に食い込む、何か特別なものを持っているんじゃないかと思っていたのだが、それは思い過ごしだった? いや、その控えめなところ、そして普通なところが、同性代の人たちから見た時の一番の魅力なのかもしれない。裏表のなく、実直で真面目な男だ。また彼のドラムに関しては、綺麗に叩いているようで、時折、暴れてバンドの音からはみ出す所が面白いな感じていた。まあ、こんなことを言われても本人は嬉しくはないと思うが。以前、ここでインタビューをした蓮池創太郎くんとのカルテットで演奏するスムース・ジャズの中、ベースの白石くんとのリズム・コンビが時折暴れ出すのが面白かったなと、今でも印象に残っている。
このサイトの取材を続けて行く中で、「どうしたら、若い人たちとうまくやっていけるんだろう?」という私の悩みを彼に話を振ってみたら、「僕も年下は苦手なんです(笑)。年上の人の方が楽ですし」と言って、笑顔を見せた。インタビュー当日は、前回の葛西くんの時に続き、終了後に一緒に酒を飲みながら話をしたが、私としては、いくら話をしても足りないくらい、そんな貴重な時間を共有してもらったと思っている。そこには感謝しかない。
さて、みなさんに山田“ローソン”祐輔くんの魅力をどのくらい伝えられただろうか? 多分、普段からもっと彼と接している若いミュージシャンたちの方が、私よりもずっとずっと、彼の魅力を知っているのだろう。この続きは、次のライヴ会場で。そしてまた、時間を作ってゆっくり話ができるのを楽しみにしていようと思う。
[ライヴのスケジュールなどはこちらで]
https://ameblo.jp/lawson-yusukedrums

葛西レオはそのクールな見た目とは裏腹に、相当な熱い男である。私が話をしていて感じたその素顔をここに綴ってみよう!
ジャズ・トランぺッター葛西レオは、かなり面白い奴である。見た目は凄くクールなのに、実は中身はかなり熱いというのが、彼と話をしてみた印象だ。ここでのインタビューは通常30分~40分程度なのだが、彼との会話は2時間半をゆうに超えていた。しかも、お互いに話し足りなかったのか? インタビューをしていた水道橋近くの彼の事務所を出て、終了後は神楽坂のサイトにも掲載している家鴨舎というレコード・バーに場所を移し、酒を飲みながら3時間近く話をしただろうか? とにかく彼の中に溢れる熱い想いを吐き出さずにはいられないという感じだったのだろう。打てば響く彼との会話に私も夢中になって、私自身もジャズや現在の音楽シーンについて感じていること、いろいろと彼にぶつけていた。そんな彼が、今の日本のジャズ・シーンについて、こんな話をしてくれた。
「今ってジャズの杯が少なくなってきているから、ジャズが好きな人以外にもアピールしていくことって大事ですよね。伝統って守れば守ろうとするほど廃れていくんで、結局コアな人間しか残ってない。今の海外のジャズってミクスチャーで、民族音楽とかとコラボしたりして、どんどん新しくなっているんで日本だけ凄く古いジャズをやっている(笑)」
物凄く率直に、ストレートにものを言う彼のその姿に感化されてか? 私もストレートに普段感じて気にしている、若いミュージシャンたちが苦戦を強いられる集客と、都内近郊に溢れかえるほどの箱の多さについて話を聞いてみると、こんな答えが返ってきた。
「お客さんがあまり入らないことを前提として、小さな箱が乱立してしまっているので、ジャズという音楽が本当に14~15人という少ない人数のためだけに聴かせる、小さな音楽になってしまっているのが凄く残念です。ジャズがメインストリームだった時代って、ホールとか数百人、数千人という人数を相手してやっていたんで、それはドジャズであってもそうだったのにです。今の東京で、これだけエンタメが乱立する中で、ジャズを聴きに来させる、そのために何をするべきなのか、その辺の考えが何もなくただの再現音楽に留まっているというのも見えますよね。それが今、ジャズの価値というものをどんどん下げて行ってるような気がしますね」
そんな彼は今日のジャズに、いったい何を感じているのだろうか?
「ジャズの伝統を見た時に、まあジャズっていうのもどんどん変わっているんですけども、やっぱり今までのジャズ・プレイヤーっていうのは前時代の継承、そして時には批判をして、その中で自分のオリジナリティというものを加えて、そうやってジャズを進歩させてきたと思うんです。それがあるから、今日のジャズがあると思うので。そういった連続性の上で~私たち日本人が何を表現するのか? っていうことが重要だと思います」
そして、こうも続ける。
「現代のジャズにおいて大事なのは個性です。個性が一番大事だと思っているので、ルイ・アームストロングの時代は、それまでがビッグ・バンドのスタイルとかのその辺に対してのアンチテーゼ的に“俺はこんな吹き方ができるぞ”とか、そういう個性って面白いねっていうところからジャズは発展してきたわけで。そして、チャーリー・パーかーが独自の理論で、それも個性で、ロジックの個性で発展させた。そして、マイルス・デイビスはサウンドの個性っていうので、それまでとは違うジャズっていうのを発展させたわけで。だから自分も個性~バンドでやるのならばバンドとどう向き合うのか? っていうところで、自分は新しいサウンドを作って行きたいんです」

個性というのは、私もずっと気になっていたところだ。若い人たちの演奏を見て聴いて、みんな上手いな~とは思うのだが、それは昔と比べて全体的に演奏技術が高くなってきているのだろう。だが、それは平均が上がったというだけで、みんながその平均点レベルに集中していて、そこからそれぞれの個性というのが見えてこないのだ。結局どういうことかというと、上手なのはいいんだけど面白くない、ということになってしまっていると私は感じている。その辺は、私と葛西レオとの共通した意見とも言えるかもしれない。
そんな彼が最初に音楽に触れ始めた時の話を聞いてみた。
「元々僕は曲を作る人間だったんです。で、幼少期に最初はピアノを習っていたんですが、そのピアノのレッスンが嫌いで嫌いで(笑)。クラシックは好きなんですけ、最初に親に頼んで買ってもらったCDもクラシックでしたし、幼稚園の年少の頃ですが。それくらいクラシックも大好きなんですけど、ピアノのクラシックのレッスンが本当に苦痛で(笑)。そこに自分なりのエッセンスというのが~バッハを弾くにも、ロマン派を弾くにも、僕はそこに自分なりのエッセンスを付け足しがちみたいなんですよね。やっぱりバッハのいた時代と今の時代とでは違うんで、好きに弾かせてよって感じだったんです。でも、そうすると先生に怒られるわけですよ(笑)、バッハはそうじゃないって。なので、僕は自分の曲を作って行ってレッスンで弾いていたんです、そうすると怒られないから。自分の曲なんで自分がどう弾こうといいじゃないですか?(笑)。そんな子供だったんです」
続いてトランペットを吹き始めた頃のことについても聞いてみた。
「トランペットを吹き始めたのは、中学の時の吹奏楽部でした。最初に影響を受けたのは、マイルス・デイビスです。彼の精神性だとか、ジャズというジャンルをどんどん進歩させて行く能力とか、あとは客観性~客観的にステージを俯瞰して見る能力とかですね。そして芸術性も。彼は自分が出す音をアートとして表現できる能力が他者とは、他の楽器~ヴォーカルも含めて彼との一番の違いだと思うんですよね。通常であれば使えないようなミストーンまでもアートに昇華してしまうという才能が凄いですよね」
そんな彼が、音楽を演奏するうえで、大切にしていることがある。
「音楽の原点って、不特定多数の人間に向けたところにあると思うんですよね。この気持ちを押さえられないから、誰かに届けたいという想い、その熱量が大事だと思うんですよね」
そう、彼の言う熱量が大事だということは、私も常々感じていることで、他者とジャズの話をする時によく口にする言葉だ。彼は、こうも続ける。
「昔のジャズって、今よりも、もっと大きなところで演奏していたと思うんです。そこでは、やっぱ音楽にそれなりの熱量が無いと伝わらないんです!」
誤解を恐れず、このような言葉を彼が口にするのは、それだけ自分自身のジャズに対しっての想いが強くて、純粋だからなのだと私は感じる。
今回のインタビューの中で、彼は「これは書けない話なんですけど~」と言って口にした話がいくつあっただろうか? それに、3時間近くに渡った会話のほんの一部しか、ここでは紹介できないのが残念だ。もし、彼の演奏、葛西レオという人間に興味があれば、ぜひ彼のライヴに足を運んで、そして演奏終了後には彼に話しかけてみて欲しい。きっとみんな、文章や写真だけでは到底伝わらない彼の魅力の虜になるだろう。ここでは泣く泣く割愛した詳しいプロフィールやライブ情報などは、彼のホームページなどで、ぜひチェックして欲しい。
https://reokasai.net/


ニューヨーク在住20年以上、熱き魂のジャズ・ギタリスト、恩人であり親友・高免信喜が私の前で語ったジャズとはいったい!?
最初にはっきり言っておこう。彼の存在が無ければ、私の辞書の中に、ジャズという音楽ジャンルは存在しなかった。もちろん、Young Jazz Magazineなんてものも作っていなかったのは、間違いのない事実だ。
そんな高免信喜くんは、私の個人的な見解で言わせてもらうと、ニューヨーク生活の中での、大親友と言ってもいい。名門バークリー音楽大学を首席で卒業し、当時ギターと言えばロック・ギターしか知らなかった私を、自身のジャズ・セッションに招いたのも彼だった(それも2度にわたって!)。当時は「なんて無謀な真似を!(笑)」と思ったものだが、今ではとても懐かしく、良い思い出の1ページと言える(ま、たいしたギターは弾かなかったのだが)。
そんな高免くんが、毎年夏、恒例の日本ツアーのため帰国している。そこを逃すはずもなく、インタビューを実施! 改めてふたりで確認してみると、およそ15~16年ぶりとなる再会だったことに気づいた!(よくそんなんで、大親友などと言ったもんだ…)。
まあ、それは置いといて、さっそく高免くんの話を聞いてみよう。まずは、ツアーの話から。
「最初、2004年に一回日本ツアーをやって、その後、2006年からは毎年帰国してツアーをやっています。休んでいたのは、2020年と2021年がコロナで帰れなかった時だけです。コロナ過の時は、ツアーだけじゃなくて他の音楽活動も駄目でした。でも、それはそれで家族との時間を大切にできたり、考えようによってはいい時間だったかもしれないですね」
今回の帰国は、奥さんと娘さんと連れ立ってということで、日本で過ごす家族との時間も大切にしており、スケジュール的にはかなり大変だったようだが、私がJazz Magazineなどというものをやり始めたこともあり、かなり頑張って時間を作ってくれたことに、改めて感謝したいと思う。
高免くんは、広島県出身で、大学から東京で暮らしていたようだ。そんな彼が、アメリカを目指そうと思ったきっかけはなんだったのだろう?
「ギターを始めた頃からアメリカの音楽が凄く好きで、21歳の時にアムトラック(注※)で、アメリカを一周したんです。それが、やっぱり大きくて、この国で音楽をやりたいなっていう気持ちになりました」
2001年に、ボストンの名門バークリー音楽大学に入学。2004年に首席で卒業し、ニューヨークに拠点を移して、もう20年以上になる。
私がニューヨークに住み始めたのが、2004年1月。引っ越してすぐ、2月にはニューヨーク・メッツのキャンプを撮影するために、長期にわたり~2カ月ちょっとフロリダに滞在するわけだが、ニューヨークに帰って来て、東京での知り合いを通して出会ったのが、高免くんをはじめとするバークリー出のジャズ・ミュージシャンたちだった。特に、当サイトでも紹介しているピアノの神田斉(ひとし)くんと、高免くん、私の3人でよくコリアンタウンやチャイナタウンに出かけては、安くて美味しいご飯屋さんを探し当てて、一緒に食事をし、時には酒を飲み、そのまま高免くんの部屋に泊まり、夜中にこそこそとギターの話を繰り返した夜も、一度や二度ではない。
元々、ロック・ギターを弾いていたという高免くん。そんな夜には、共通の好きなギタリスト、日本ヘヴィ・メタルの雄・ラウドネスの高崎晃の話で盛り上がったりもした。そんな彼が、ジャズ・ギタリストを目指したきっかけはなんだったのだろう?
「ジャズをやるきっかけになったのは、やっぱりアドリブですね。即興演奏です。即興演奏をするには、ジャズをやった方がいいというのが最初でした。初めは本当にこれをやらなきゃいけないという感じだったんですけど、だんだんとそういった演奏が好きになってきたんです。それで、ウェス・モンゴメリーを聴こうみたいな感じがあったんです。でも、最初はあまり好きになれずに、しっくりこなくて。やっぱり自分が元々好きだった、ロックやブルースの匂いがするブラント・グリーンとか、パット・マルティーニが好みだでした。彼らが凄くいいなと思って。で、彼らを聴いてからウェス・モンゴメリーを聴きなおすと、その良さも凄くわかるようになって。実際に、僕はパット・マルティーニさんとお会いしたことがあるんですけど、彼も凄くウェスに影響を受けたと言っていたので、やっぱりその辺って繋がっているんだなと思い、嬉しくなりました」
私が出会った頃には、高免信喜はもうとっくにバリバリのジャズ・ギタリストだったわけだが、特に彼の中ではジャズ云々という話は無く、同じギタリストとして、話の相手になってくれたことが嬉しかったのを凄く覚えている。そんな彼の、音楽に対してのフラットな考え方が無ければ、今頃、私はジャズ嫌いになっていたかもしれない(実際、そうじゃない人もけっこういるのだ)。

そんなジャズのことをよく知らない私が、彼に「ジャズってどんな音楽?」と問うと、意外にもこんな答えが返ってきた・
「ジャズっていうのは、けっこうバンドの音楽なんです!」
高免くんに言わせると、コルトレーンもマイルスも、かの巨匠たちの音楽も、バンドの音楽だったのだと言う。
さらに、ロック・バンドしか経験のない私が、年に1度のツアーのことを聞くと、こんなふうに語ってくれた。
「基本的には、何年経っても、毎回毎回、ベストを尽くすっていうのは変わっていないです。よく、ジャズはバンドの音楽ではないと思われるかもしれませんが、ロック・バンドがコンサートに向けてスタジオにこもって何時間もバンド練習をするように、僕らにもそこに辿り着くまでに、何十時間も何百時間も練習を積み重ねてきた時間があるんです。それはもちろん、今回の演奏に向けてでもあるんです。僕らは、ジャズという音楽で会話ができるように、ずっと日々、練習に取り組んできているんです。それがジャズ・ミュージシャンという感覚かもしれないですね。今回も、棚橋くん(Ba)、會川さん(Dr)という素晴らしいメンバーと一緒にやりますけど、彼らのことは凄い信頼していますし、そこに向けて僕らはずっと努力をしてきた、積み重ねがあると思っています」
ベースの棚橋くんは、このサイトでも紹介している高免くんのバークリー時代からの盟友で、私もニューヨークでちょっと交流があり、今年はじめに、あるシンガーをきっかけに東京で再会をしたミュージシャンだ。
さらに、高免くんはこんなことを言った。
「ジャズっていうのは、本来、自由なものだと思うんです」
ナント! ジャズは自由なんだ! 尾崎豊さん以外の口から、音楽について自由を語られるとは思ってもみなかった!
冗談はさておき。ジャズという音楽が、本当に自由なのだとしたら、ジャズはなんて素晴らしいものなのだろうか!! 私が関わってきたジャズという音楽の中で、“自由”を感じられたとしたならば、それは「上原ひろみ」と「高免信喜」以外には考えられない!
最後に高免くんは、ジャズが素人のJazz magazine主催者に、こんな話をしてくれた。
「感じるのは、コミュニティの大切さですね。ジャズっていうのは、ソーシャル・アートで、みんなで作って行くものなので。僕が属している、今のニューヨークっていうコミュニティで学んだことっていうのは、凄く大きいですよね。けっこう今の時代、ユーチューブとか見ていると、僕は他人のことを悪く言うのは好きじゃないんですけど、悪く言っている人が多いんです。例えば“そんなのはジャズじゃない”とか。でも、そういう人たちに欠けているのは、…僕はジャズ・レジェンズと一緒に演奏できるという感じではなかったですし、僕がニューヨークに立った時はコルトレーンもいないし、マイルスもいないし、でもそういう人たちの演奏に生で触れたっていう人たちや、一緒に演奏したっていう人たちと一緒に演奏する機会はあって、そういう人たちと一緒にやっている時に、お前のそれはジャズじゃないとか、そういうのって一切無いんですよね。そこが、僕がニューヨークに行って、自分はまだまだ良い演奏ができない、そういう人たちって歩いている姿から違うっていう感じなんですよね。そういう大ベテランたちっていうのは。でも、自分の演奏に駄目出しされるわけじゃなくて、keep doing,what you doingっていう、今やっていることを頑張ってやれ、みたいな。そうすれば、できるようになっちゃうよみたいなね(笑)。長い目で見てくれるみたいな。そうやって、コミュニティの中で成長していくというのを、自分も大切にしていきたいですね。あとは、いかに自由になるかっていうのを、ニューヨークで学んだ気がしますね」
高免くんの言ってることは、私も、もっともだと思う。そうなのだ。自由の国アメリカ、自由の街ニューヨーク、私たちが憧れたものは、そこだったはずだ。
そして彼は、こうも続ける。
「ジャズっていうのは、アマゾンのレビューがすべてではないんですよ。ユーチューブの再生回数がすべてではないんです。そこで、自由が奪われてしまっている気がしますね。ジャズっていうのは、決して否定から入らないと僕は思うんです」
愛と自由に満ちた、ジャズ・ギタリスト高免信喜。それは、自分が憧れたロック・スターの姿を見ているようだ。長い付き合いだと思ってはいたが、改めて高免くんの話を聞いていて、彼のミュージシャンとしての姿の素晴らしさに、本当の意味で気づいていなかった自分が恥ずかしく思えた。高免くん、ごめん! きみは、本当に素晴らしいミュージシャンだ。そのギター・テクニックはもちろん、その音楽に対する考え方もとても素晴らしい! 今、改めてきみの素晴らしさに気づかせてもらったよ…。
大事なツアーは、これからが本番。スケジュールは下記、彼のホームページにてみなさん確認してほしい。
ニューヨークを離れて、もう十数年。その間、一度仕事でニューヨークを訪れたきりで、しばらくニューヨークには行っていない。コロナ過も明け、面倒なトランプ政策も緩んだ頃を見計らって、また高免くんや仲間たちに会いに、ニューヨークを訪れてみたいと思う。その時は高免くん、またよろしくね!!
注※アムトラック=全米鉄道旅客公社。全米を結ぶ、公共鉄道路線。ニューヨークからだと、ボストンやフィラデルフィア、ワシントンD.C.を結ぶ路線が有名。


北の大地が生んだ天才サックス・プレイヤー寺久保エレナ、デビューまでの真実!
※このインタビュー記事は、寺久保エレナのデビュー前に米田が独自に取材して、「Swing Journal」2010年7月号に寄稿したものをベースに、新たに書き起こしたものである。
衝撃のデビューだった。当時、まだ18歳になったばかりの高校3年生である。まだ、札幌の実家に住み、札幌を拠点に道内外に活動の幅を広げていた彼女。
その音楽歴は、幼少期のクラシック・ピアノから始まり、9歳でアルト・サックスを吹き始めてジャズに興味を持ち始めたと言う。その翌年から札幌ジュニア・ジャズ・オーケストラに参加すると、瞬く間にその非凡な才能を発揮し始めた。その噂は各方面に広がり本田雅人をはじめ、渡辺貞夫、タイガー大越、日野皓正、山下洋輔といった大御所たちにも認められ、ステージでの共演を繰り返した。
「最初に憧れたのは、本田雅人さんです。私はサックスを始めた頃からプロになりたいと思っていましたし、本田雅人さんの影響は大きいですね」
13歳の春に、「バークリー音楽大学タイアップ、北海道グループ・キャンプ」に参加し、最年少でバークリー・アワードを受賞。2007年から2009年まで、奨学生としてバークリー・サマーキャンプに参加。
「バークリーでは、本当に刺激を受けました。参加している生徒たちの競争心が、物凄く強いんです。なので、私ももっと頑張って勉強しなきゃという気持ちにさせられました」
その前年、2006年の室蘭ジャズ・スクールのセッションでは渡辺貞夫と共演し、こんなエピソードがあったという。
「渡辺さんとセッションの時に、ステージに上がって譜面台を立てたら、それを渡辺さんにガシャーンと倒されて、“自由に演奏しないと駄目だよ”って言われたんです」
また、山下洋輔とは2008年の新宿ピットインのライヴに飛び入りで参加し、翌年からは2年連続で山下が彼女をフィーチャリングしてライヴを行った。それが縁で、デビュー・アルバムのリリース時に、山下から書下ろしの新曲をプレゼントされた。
「でも、山下さんっぽくない曲で(笑)。やっぱり私を意識してくれたんだと思います」

デビュー・アルバムの録音は、2010年4月にニューヨークで行われた。彼女にとって、初めてのニューヨークは刺激的なものだったようだ。
「ボストンよりも、ニューヨークの方がぜんぜん好きになりました。凄くたくさんジャズ・クラブがあって、いろんな場所で凄い人たちがたくさん演奏しているんですよね!」
実際のレコーディングでは、こんなエピソードがあったと話す。
「すべての曲を、私のアレンジでやってもらったんですけど。『ステイブルメイツ』と私のオリジナル『ライク・ザ・サンライト』で、ピアノのケニー・バロンが“このアレンジは難しいから、ちょっと練習させてくれ”って言うんですよ。でも、アレンジを変えることは考えなくて、やっぱり自分の思い通りに作りたかったので…」
どんな相手にも妥協しないその姿勢は、もうすでにプロとしての自覚、自信を感じさせた。
また、当時彼女は、そのデビュー・アルバムに対して、こんなコメントを残している。
「私の個性、オリジナリティが凝縮された作品なので、たくさんの人たちに聴いて欲しいです。私の目標は世界です!」
日本のジャズを変える新星が、産声をあげた瞬間だった。

ニューヨークの奇才、ジョン・ゾーンの意思を継ぐサックス奏者、吉田野乃子が考えるジャズとは? そして音楽とは?
フリー・ジャズ、あるいは前衛音楽とも言うべきプレイスタイルで、精力的に活動を続ける吉田野乃子。彼女は自分の音楽、あるいは出す音を“ノイズ”と表現することが多い。その独特のスタイルはどのように誕生したのだろうか?
「サックスを始めたきっかけは、元々両親が音楽好きで、10歳の時に小学校にスクール・バンドがあって、小学生で管楽器が吹けるのも珍しいかなと思って。私の中で楽器とその名前が一致していたのがサックスくらいだったので(笑)、それがきっかけです」
インタビュー冒頭、私の最初の質問に対する彼女の答えは、何とも普通の可愛らしいとさえ思えるものだった。彼女はこう話を続けた。
「両親が、“ジャズは楽しいよ、楽譜にとらわれない自由な音楽は楽しいよ”って言うんです。その父親から、山下洋輔さんのフリー・ジャズを聴かされていたのが、自分の一番古い音楽の記憶としてあって。父親が“これがカッコイイ音楽なんだ”っていうわけですよ。それで私も、いずれはフリー・ジャズみたいなカッコイイ音楽をやりたいなって思っていたんです」
そのご両親の影響もあり、自由にジャズを楽しむ環境を与えられた彼女は、自らジョン・ゾーンや林栄一、板橋文夫といったミュージシャンたちの演奏にのめり込んで行く。そんな彼女は、二十歳を前にして、単身渡米を決意し、ニューヨークへと渡る。実は、私が彼女と知り合ったのが、そのニューヨークだった。ニューヨークという日本から遠く離れた街で、私たちはともに“北海道出身”というキーワードで繋がった。彼女は、こう話を続ける。
「フリー・ジャズをやる前に、ちゃんとスタンダードもやらなきゃ駄目だよって言う人が物凄く多くて。ならばちゃんと本場で勉強してやろうと思って、だからニューヨークだったんですね。ちゃんとジャズが生きている国じゃなきゃ駄目だと思ったんです。で、行ったら行ったで、すぐジョンに出会えて。そこで、フリー(ジャズ)をやりたいなら、スタンダードを勉強しなきゃいけないルールなんて一個も存在しなかった。ジョンにも“そんな勉強は今すぐやめろ”って言われました。それは私にとって物凄い発見だったんです。そこからノイズの勉強はするし、自分で変な曲を書いてみたり(笑)、そんなことばかりしてました」

彼女が今も師と仰ぐジョン・ゾーンとの出会いについては、こんな話もしてくれた。
「最初はレッスンをしてくれるといいなと思ったのですが、サックスのレッスンはやってないけど、音楽の話をすることはできるよって言われて。ジャズを勉強しに来たのですが、本当はあなたのやっているような音楽が好きなんですって言ったら、それならジャズの勉強なんかしなくてもいいって言われて、凄くビックリしたんです。その後、レコーディングに連れて行ってもらったり、取材の時に横で一緒に話を聞かせてもらったり、ホント、お父ちゃんのように可愛がってもらえたんです。そんな感じで、早いうちにジョンと出会えたのはとても幸運でしたね」
ニューヨークとの関係については、こんな風にも語っている。
「ニューヨークって、ジャズの本家を聴ける街じゃないですか? 本家がいるのに、私がそのカバーをやることは意味が無いって思っちゃうわけですよ。オリジナル曲って、その作曲家のむちゃむちゃ個人的な思いだったりすると思うんです。だから、他の人がカバーするのはなんか変なんじゃないかって。自分で曲を作ることは、とても大事なことだって最初に師匠から教えられて。師匠に昔の演奏の映像を見てもらったんですが、その中でコルトレーンの曲を演奏していたんですけど、“コルトレーンの曲は彼が演奏してるんだから、君はやらなくていい”と言われたんです。その次に、自分が書いたへったな曲があって、“絶対にこっちの方が素晴らしい。何故かというと、君の曲は君が一番うまく吹けるんだから”って言うんです。それは凄い言葉だなと思いました」
そうしてジョン・ゾーンに音楽を教わりながら、同じく彼の周囲にいた若手ミュージシャンたちとバンドを組み、ニューヨークで音楽活動を続けていた彼女だったが、しばらくして家庭の事情で、北海道岩見沢市の実家に戻ることになる。それでも彼女はそれをマイナスと捉えず、家賃のために音楽以外のアルバイトを頑張ることも無くなって、逆に良い環境になったと語っている。
今も、その地元岩見沢と札幌を拠点に、道外はもちろん、時には海外のフェスにも参加するなど、その活動はかなり精力的だ。今回のインタビューも、ツアーの関東シリーズの途中に行われた。彼女は最後にこんな話をしてくれた。
「今の私があるのは、師匠や周りの人間に恵まれていたからなんです。ニューヨークでも、どこででもです。だから、今も私はこうして音楽を続けられている。そこには、絶対的な感謝しかないです」
北海道からニューヨークへ。そして北海道から世界へ。これからも彼女の信じる音楽をどんどん発信して行って欲しいと思う。
https://nonoyarecords.themedia.jp/


東大法学部卒! クラシック・ピアノで数々の実績を残す若干26歳のピアニスト。蓮池創太郎はいったい何を語ったのか!?
東大法学部卒! しかもクラシック・ピアノのコンクールで優秀な成績を収めたピアニスト! で、ジャズ??? まあ最初はそんな安易な見出しにつられて声をかけたのだが、実際に会って話をしてみるとそんな堅苦しさはまったくなく、髭面の下に童顔が見え隠れする、なかなか爽やかな青年だったのだが。そんな、若干26歳のジャズ・ピアニスト、蓮池創太郎くんに話を聞いてみた。
「ピアノを始めたきっかけは、家にピアノがありそれを自由に弾いていたところ、母親が地元のピアノの先生のところに僕を連れて行ったというのがきっかけです。4歳の時ですね」
まあまあ、この辺は、よくある普通の話である。先を続けよう。
「基本的には、ずっとクラシックでした。小学生の頃は、出身地の九州のコンクールなどで優勝させてもらったりして、かなり有名な先生にも教えて頂くことがありました。横山幸雄さんとか上田晴子さんとかですね。それでレッスンを受けさせて頂いて、クラシックを続けていました。中学生くらいから、ちゃんとコンサート・ピアニストとしてやって行こうという思いで、練習環境を整えて、音楽的な勉強も始めたんです」
まだまだ、クラシックの話は続く。
「高校1年生くらいから本格的にクラシック・ピアニストで行こうと思い、最初は東京芸術大学を目指してたんです。でも高校に入ると、勉強も本格的になってくるじゃないですか? で、勉強を進めていくと大学進学に当然繋がるわけです。それまでは、自分は音楽しかやってこなくて、でも他にもいろんな世界があるんだなと高校生活の中で学び、もう少しいろんなことを学んでみたいなと思ったんです。そこで芸大ではなくて一般大学を受けてみようかとなりました。それでもピアノは続けられますし、一般大学でいろんなことを学んでみたいなと。それで2年生の時に進路転換し、一浪の末東大に合格しました」
う~ん。簡単に進路変更をして、それが芸大から東大とは…!!

「東大に入って、最初はいろんなことに興味が行ったんですけど、でも本当に自分が熱量を持って向き合えるのは、やっぱり音楽だなと思って。そこで音楽をしっかり勉強しなおそうと思いました。大学2年生の時に、ショパン国際ピアノコンクールin ASIAっていう大会があって、他に芸術系の大学の方たちもいる中で、僕もアジアで入賞させてもらうことができました。で、本格的に音楽活動をと思った矢先、コロナ過になってしまい、いろいろ企画もしていたんですけど、それも無くなってしまって…。人前でピアノを弾く機会も無く、それで大学3年生くらいから作曲を始めたんです」
世代的に、ちょうどこれからという時に、コロナの直撃を受けてしまったという、何とも残念な感じだが。でも、それを彼は作曲を始めるという方向転換で、うまく自分のプラスへと切り替えた。
「作曲を始めて、誰かが決めた音を出すのではなくて、自分で自由に音を出せるのは楽しいと思いました。それがジャズの即興にも繋がっています。僕の場合、クラシックから作曲、そしてジャズという流れなんです」
そのジャズについてだが、彼はこんな話をしてくれた。
「ジャズは高校時代から聴いていて、僕はストレートなジャズが好きでした。バド・パウエルとかフェニアス・ニューボーンJrとかが、僕は大好きだったんです。あとはキース・ジャレットとかもですね」
正統派! 自身が語るように、入りは実に真っ当な入り方だったようだ。そこから、どんなスタイルの変換があったのだろうか?
「きっかけはセッションです。元々はストレートなジャズが好きなんですけど、最初はフュージョンとかファンク系が多かった。そういった中で、徐々にジャズのライヴにも誘ってもらえるようになって行きました。下北沢のrpmっていう店に出入りしていたんですよね。ジャズは、椎名豊さんに師事していたんですけど、椎名さんは他にもたくさん教えていらっしゃって、若手のジャズの方たちもたくさんいるんです。そういうところでの繋がりもありました」
本来なら、ジャズ・マガジンというからには、この辺の話からスタートするものだが、それが蓮池創太郎というピアニストの個性だろう。また、クラシック出身らしい、こんな話もしてくれた。
「クラシックは非常に難解な技術が必要とされるので、ジャズをやっていて指が動かないとか、技術的に不可能だと思ったことは、ほとんど無いんです。どんなテクニカルなものでも、弾けちゃう。その一方でリズムとか、グルーブを全体で共有してっていうところが難しい。その辺は、感覚をブラッシュ・アップするというか、一度自分の中で新しいものに書き換えて行く作業が必要になってしまう難しさがあるんです」
よくジャズは、スイングするという表現を使う。要はノリとかリズムということだが。確かにジャズには、クラシックには全く存在しないグルーブやリズム、ノリがあり、それが必要不可欠で、ジャズ・ミュージシャンと称するのなら、そこを表現できないと批判の対象にもなりかねない(本誌ではそんなことは決してないのだが)。
「ストレートなジャズだと、まだクラシックと共通する部分もあるんですけど、コンテンポラリー系を弾くとやっぱり“クラシックっぽいね”って言われることもあります。それはそれで受け止めてはいるんですけど。そういった部分では、まだまだ僕はジャズとは遠い部分も少なからずあるのかなと思います」
プロのミュージシャンにとってもし個性が命と語る人がいるのなら、彼みたいなプレイヤーこそ、プロに近いのかもしれないとも思う。現在彼は、新たなリーダー・ライヴを見据えている。
「リーダー・バンドは、3回目になりますが。以前来てくれた方には、僕のオリジナルに対しての評価が高かったんです。そこは純粋に嬉しかったですね。とはいえ、もっと経験も必要かなとも思いました。今回は、より自然に、肩肘張らずに、音楽を楽しんでもらえると嬉しいですね。最終的には、楽しい音楽をやりたいですしね」
26歳で、まだジャズに転向して3年。しかも、現在彼は、ジャズだけではなく、ロックやポップスのセッションでも活躍している。蓮池創太郎というピアニストは、ジャズに対してまだまだ大きな可能性を秘めている。ならば、彼の今後を、成長を見守って行こうじゃないかと思う。
※蓮池創太郎リーダー・ライヴ 5月1日東中野セロニアス
